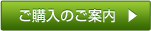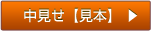縁起担ぎのはなし〜福をかき集める“酉の市”
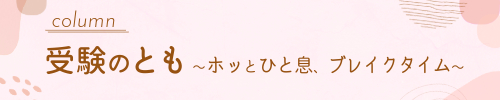

第24回:縁起担ぎのはなし〜福をかき集める“酉の市”
11月に入り、いよいよ受験勉強の追い込みや受験先の具体的な絞り込みなどで、
緊張感も高まるころかと思います。
推薦入試などを受けている人は発表もそろそろでしょうか。
進学先がすでに決まった友人などがまわりにいて、
なにかと落ち着かない日々が続いている人もいるかもしれません。
勉強を頑張れば頑張るほど、入試日程が見えてきたからこそ、
あせりや不安がつのるのはあたりまえのこと。
これまでの努力と今の自分を信じて、あと少し集中していきましょう。
その上で、やってきた努力がより大きく実るように、
今回は縁起担ぎの行事に注目してみました。
11月といえば、大きな熊手をかかえた人の姿がニュースにもなる“酉の市”。
年末が近づく風物詩として目にしたことがあるのではないでしょうか。

酉の市は毎年11月の“酉の日”に行われるお祭りで、
商売繁盛、開運招福を願う、江戸時代から続く年中行事のひとつです。
諸説ありますが、元々は農民の収穫祭が起源とされており、関東を中心に行われています。
酉の市の“とり”は、生き物の鳥ではなく、十二支の酉。
子(ね)・牛(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)。

十二支は日や月の数え方、方角を示す方法として、
古代中国で用いられていたものでそこから暦が生まれ、日本にも伝わりました。
自分の誕生年を「わたしはねずみ年!」などと話したことはないでしょうか。
その干支です。
年の干支が12年に一度巡ってくるように、日を表すそれぞれの干支も12日に一度順に巡ってくるため、
毎月少なくとも2回(多いときは3回)は酉の日がやってきます。
ちなみに酉の市が行われる2025年11月の酉の日は12日と24日。

最初の酉の日は“一の酉”、2度目の酉の日は“二の酉”と呼ばれ、
各地の神社などで盛大にお祭りが催されます。
そして、酉の市といえば縁起物の“熊手”。
落ち葉などをかき集める道具として使われる熊手ですが、
その使い方から、「運や福をかき集める」「金銀をかき集める」とされ、
開運招福や商売繁盛のお守りとして授与されるようになったのだそうです。

市でも、宝船や大判小判、米俵、稲穂、絵馬、小槌や升などといった
縁起のよい飾りが施された、華やかで豪華な熊手が売られています。
大きければ大きいほど運が大きくなるともいわれ、
毎年多くの人が熊手を求めてお参りに訪れます。
関東三大酉の市のひとつといわれる東京・浅草鷲神社の酉の市では、
熊手を売る店が約70店余りも並ぶことでも有名です。

熊手には商売繁盛のほかに、家内安全、健康や合格祈願などさまざまな願いが込められたものがあり、
開運・招福飾りのバリエーションも豊富。
運や福を大事にしたい受験生にとっても、ぜひとも欲しい縁起物のひとつといえるでしょう。
タイミングがあえば、酉の市が行われる近所の神社に足を運んでみてはどうでしょうか。
合格祈願のラッキーアイテムを手に入れ、神社で新鮮な空気を吸えば、
勉強で疲れた心身のよいリフレッシュになりますよ。
ちなみに酉の市で入手した熊手は、その後の取り扱いにも気を配りたいもの。
まずは目につきやすい、人の頭の位置よりも高い位置に飾ります。
福をかき入れるという意味では玄関や入り口に、神棚があればそのそばに。
また、正面北に向けて飾ることは避けたほうがよいともいわれています。

合格祈願なら、志望校の方角に向けるのもよいかもしれません。
運も実力のうち。
そんな言葉もありますから、この時期、縁起物の熊手の力を借りて、
残りのひと踏ん張りに弾みをつけてみませんか。

参考資料:『日本の四季と花鳥風月を愛でる 365日、暮らしのこよみ』
プロフィール
文/野々瀬広美
編集・ライター。生活実用の出版社3社での会社員生活ののち、フリーランスに。暮らしまわり・ハンドメイドのジャンルを中心に取材・編集・執筆などを手がける。編み物とサッカー観戦が好き。図書館司書の資格を持つ。