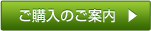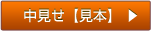親子で一緒に! 食生活のちょこっと改善を
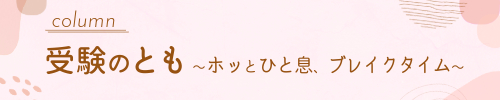

第13回:親子で一緒に! 食生活のちょこっと改善を
受験本番の年度に入り、机に向かう時間が増えてくる時期かと思います。
1日の過ごし方が勉強に偏りがちになり、
食生活がこれまでと変わってきたなと感じている人はいないでしょうか。
部活も引退してしまったし、運動ができなくて体重が増え気味だから、
朝ごはんは食べない、栄養補助食品をちょこちょこつまんでやり過ごす、
など勉強優先で、食をおろそかにしているようなら要注意です。

長い受験期間を乗り切るには、体力・筋力をつけたり、
脳の働きや集中力を高めたりするのに、食生活はとても重要になります。

簡単にできるおすすめの食べ方や栄養素の取り方、
意識したい点などについてご紹介しますので、できるところから取り組んでみましょう。
まず、いちばん簡単なのは
「よく噛んで食べる」ことです。

勉強の合間に食事をすると、どうしても早食いになり、
あまり噛まずに飲み込みがちになります。
けれどよく噛むことで唾液が出て、消化酵素の分泌が促され、栄養の吸収力がアップ。
血流も良くなり、脳がすっきり。勉強に対する集中力も高まります。
よく噛んでゆっくりと食事をすることは、勉強のインターバルにもなり、
簡単なのにいいことづくめです。
また、よく噛むための献立の工夫としては、噛みごたえのある食材を取り入れること。
野菜をいつもより少し大きめに切って炒めたり煮たりする
繊維質の多いごぼうや海藻、きのこや豆などを食事に取り入れる

など、日々の食事をがらりと変えなくても、やれることはたくさんあります。
できる範囲で始めてみるとよいでしょう。
おやつなどの間食には、ナッツやチーズ、
りんごなどしっかり噛む必要があるフルーツなどもおすすめです。
噛む回数は20〜30回ほどが目安。
私はけっこうちゃんと噛んでいるはず!という人も、数えてみると、
意外と噛んでいなかったということに気づくかもしれませんよ。

外食時やお惣菜を購入するときにも“よく噛む”食材を意識して選べば、
無理なく実行できるはずです。ぜひ習慣にしてみましょう。
次に意識したいのは、
「1つの食材に偏らない」こと。
長期的に体調を整えるには、
ひとつの食べ物に偏らず、バランスよく取ることが肝心です。
ちょっと便秘気味だからごぼうばかり食べている、
体重が増え気味で糖質が気になるから、ご飯は食べないようにしている、
など一見健康に気を配っているように思えますが、
偏り次第で、足りない栄養も出てきてしまいます。

「まごわやさしい」という言葉はどこかで聞いたことがあるでしょうか。
栄養バランスを整えるために、食事に取り入れたい食材の頭文字からとったキーワードです。
「ま」は豆、
「ご」はごま、
「わ」はわかめ(海藻)、
「や」は野菜、
「さ」は魚、
「し」はしいたけ(きのこ類)、
「い」はいも類。
これらの食材には、健康な体を作るのに必要な栄養素、
たんぱく質、カルシウム、食物繊維、ビタミン、脂質などが含まれています。
これにご飯の炭水化物(糖質)が加われば、自然とバランスのよい食事が組み立てられるというわけです。
特に魚(特に青魚)に多く含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)は、
記憶力や学習能力を高めるのに効果的という研究発表もあり、
ぜひ取り入れていきたい食材のひとつ。
ただ、肉料理のほうが子どものテンションも上がるでしょうし、
普段、肉が中心の食卓の場合、魚を取り入れるのは少しハードルが高いかもしれません。

そんなときは、
ツナ缶(まぐろ)やサバ缶をサラダや和え物に加えたり、
いつものみそ汁に市販のイワシのつみれ団子を入れたりして、
副菜に魚をプラスするのも手軽でおすすめです。
「まごわおいしい」
言葉は知っていたけれど、現実的には忙しくてなかなか取り入れられなくて・・・
という人も多いと思います。
そんなときはどれか一つ、いつもの献立にプラスしてみませんか。
まずは週に1度でもかまいません。
余裕があるときに、ちょっとやってみて、それが自分のペースに合って、
食事がおいしいなと感じられたら続けていけばよいと思います。
作る方も、食べる方も無理なく、おいしくてバランスの良い食事がとれるよう、
心地よいペースで健康な食習慣を整えていきましょう。

プロフィール
文/野々瀬広美
編集・ライター。生活実用の出版社3社での会社員生活ののち、フリーランスに。暮らしまわり・ハンドメイドのジャンルを中心に取材・編集・執筆などを手がける。編み物とサッカー観戦が好き。図書館司書の資格を持つ。